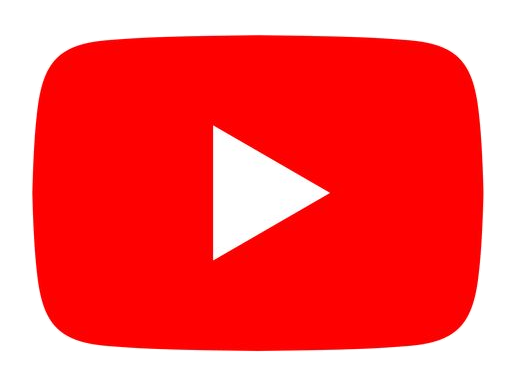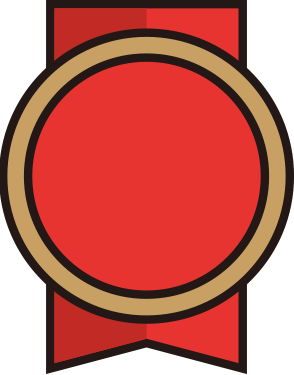【514支援者様向けおまけ絵付き】うちの子 伏見向沙苗 発情期子作りえっち絵へ繋がるキャプション
雛子に最初の子供が産まれて少し落ち着いた頃の沙苗キャプションです! ―――――――――――――――――――――――――――――― 秋も深まり少し肌寒くなってくる10月、某所。 「…こうして二人でゆっくりするのも、5年ぶりくらいでしょうか。」 大きめの帽子とサングラスを身につけて、普段はあまり着ることのない洋装で紅く染まる川沿いを夫と並び歩く。 「ふふ、この辺りはずっと変わらず綺麗なものですね。結婚した頃と同じ。」 そう言って軽く手に触れ指を絡めると、照れたのか夫が頭を掻きながら小さく笑う。 「あら、年甲斐もなくすみません。」 夫の表情にこちらまで照れが出てしまい指を離そうとすると、夫はこちらも見ずに大きな手で握り返してくる。 普段あまり積極的に何かを言う人ではないけれど、こうして行動に出して応えてくれるのが嬉しくて思わず微笑む。 許嫁として伏見向に入り、女将としての修行の日々。 結婚してすぐに雛子が産まれて、忙しくしている間に小春と小宵が産まれてと、なかなか遠く外に出る時間もない私達にとってはこの風景も久々だった。 こうして流れる夫婦水入らずの時間が私はとても好き…なのだけれど…。 「あっ…!」 唐突に強い風が吹き、帽子がふわりと川の方へと飛んでいく。 二人して慌てて帽子を追いかけ、先に帽子に追いついた夫が拾い上げる。 「あ、ありがとうございます…。もう、急にあんな風…ごめんなさい、気をつけますね。」 私にかぶせてくれたお礼を言いながら、誰も見ていなかったなと辺りを見回してほぅと安心する。 …夫と私が慌てた理由は、帽子が川に落ちてしまうかもしれないという事とは別に理由がある。 風で飛ばされていた間、私の頭にはぴょこんと獣の…正確には狐の耳が生えているのが露わになっていた。 帽子はおしゃれや日除けの為ではなく突飛なそれが人目につかないようにというもので、サングラスにしても奥で光る金色の目を隠す為。 「危ないところでした、こんな所誰かに見られたら…ってあぁもう勝手にまた…ごめんなさい。」 狐の耳がぴこぴこと動いて帽子が揺れているのを夫に注意され、赤くなりながらまた謝る。 こんな目立つものが油断すると勝手に動いてしまうから困る。 「全く、困ったものだわ…。」 この耳や目はこれはもちろん飾り物でもなんでもなく、本当に狐のそれ。 ――私の旧姓である稲荷田の家系の女には古くから狐の血が流れていて、私の巫女としての能力もその血によるものが大きい。 ただ、代を重ねていくうちに狐の血も薄くなっている為生まれつき狐の特徴を持っていたりということはないけれど、今の稲荷田の女は多少の霊的な力があるだけで見た目としては普通の人と変わらない。 それでも霊的な力を強く使う際などにははっきりと顕れてしまうもので、あまり人前で力を使うことはないようにと言う事は小さい頃から厳しく言いつけられていた。 今も力なんて使っていない、でもこうして帽子ひとつで慌てて走り回るような事になっている。 …もちろん、これには理由がある。 代々、稲荷田の女は初潮を迎えて少し経った頃…大抵13~4歳あたりから「男と交わりたい・子を産みたい」という強い願望が止められなくなる時期が来る。 はっきり言ってしまえば、稲荷田の女には動物と同じ「発情期」がある。 その時には狐としての特徴、耳や金色の目などが強制的に顕れてしまい、血が濃い場合はしっぽが出たり顔や体つきまで狐に近くなったともと聞いている。 そういう強く狐の血が出てしまった代ではあまりに強い発情に村の男総出で…ということもあったとのことだけれど、本当なのかは定かではない。 とにかくそういう初潮を迎えたばかりの娘が本能のままに手当り次第の男と交わるのは良くないということで、村で一番精力のある男1人を発情期を乗り切る為の「鎮め手」を(大抵は許婚として)迎えるようになったらしい。 そう言った歴史からの名残が実家周辺に未だ残る許婚制度で、一般の人にとっては時代錯誤なものでも稲荷田を含めたいくつかの家系には重要なことだった。 「……。」 ふと過去のことを思い出す。 初めての発情を迎えた時はぐしゃぐしゃに泣いて謝りながら夫と交わっていた記憶がある。 当時14歳だった私はまだ未成熟な身体でめちゃくちゃにしてくれと懇願して、夫が気を失いかけてからは私が上になって1人で何時間も腰を叩きつけていた。 全て終わった後に衰弱した夫を見て、なんてことをしてしまったのか、なんて役目を課してしまっているのかとひどく落ち込んでしまいしばらく夫とは目も合わせられなかった。 その時はその時で色々あって乗り越えることは出来たし、夫との絆も間違いなく深まったけれど…。 出来れば娘達にはそんなことがないようにとは思っても産まれてくる子の血の力をどうにかなんて出来るわけもなく、雛子や小春・小宵が狐の力を持ってしまうかどうかは運でしかなかった。 「はあ…雛子はそういう願望が人より少し強いくらいで済んでいますけど、小春と小宵は私の血が濃いみたいでそろそろ大変な時期になるかもしれませんね…。」 狐の血…今の所これを知っているのは伏見向の人間では夫と大女将だけで、娘達も知らない秘密。 力が強く出ている小春達はそろそろ最初の発情期を迎える頃だろう、思春期の子には敏感な話ではあるけれど折を見て色々打ち明けておかないと…。 とはいえあの子達の状況については薄々察しもついていて、どうやら鎮め手についてはこちらで用意する必要はなさそうだった。 色々と複雑な状況だしあの子狐2人を1度に相手するのは色々な意味で大変かもしれないけれど…でもあの子達が本気ならそういう関係もありなのでしょう。(夫を納得させるのは難しそうだけれど) とにかくサポートはしてあげないと危ないかもしれないから準備はしておかないと。 …ずく…。 「…ん……、まあ…今は自分のことですね。」 軽いため息をつきながら、重く疼く下腹に顔をしかめる。 予兆があってから大女将に無理を言って休暇を貰い、実家から遠く離れたこの地に来るのももうこれで5度目。 「あ、そろそろですね。」 川沿いを離れて角を曲がると大通りの奥に温泉旅館が遠くに見えてくる、稲荷田の人間を鎮める時には最優先で貸し切りとなる事がずっと昔から取り決められた場所。 管理も行き届いて歴史もある素敵な所だけれど、訪れる目的を知られている気恥ずかしさもあって素直にそれを楽しめたことはあまりない。 発情の頻度や強さ自体は歳を取るごとに減り閉経とともに完全になくなるので、制御が難しい発情は今回が最後だろう。 私の場合はあと2、3回で発情期が来ること自体もなくなるのだろうけれど、難儀な体質だなと思うと同時に毎度それに巻き込んでしまう夫への申し訳無さも出てくる。 こんな体質やこうして毎度急な遠出になる事もそこまで気にしていないのはわかっているけれど…。 「あの、ごめんなさいあなた。もうあと何度も起こらないと思いますから…」 それでも俯き気味にこの状況を謝ると、夫は立ち止まって私に向き直る。 私も立ち止まり、恐る恐る夫の顔を見上げる。 夫はとても真剣な表情で真っ直ぐに私の目を見てから口を開いた。 ――――…。 「あ…」 夫が口にしたことはある一言だけ。 けれど、それには私を十分に安心させるだけの力があった。 「あ、ありがとうござい、ます…」 真っ直ぐな言葉と視線に、お礼の言葉を言いながら嬉しいような恥ずかしいような気持ちで視線をそらす。 私には感知出来ないのだけれど、どうも夫は無意識に言霊に近いものを使っている気がする…。 ―――……。 どぎまぎする私に夫が耳元である言葉を加える。 「ちょ、ちょっと、やめてくださいそんな…もう…!」 囁かれたのはとても言えないような言葉だけれど、稲荷田の人間と許婚の関係になったということはまあ、発情期の女を鎮めるだけの精力を持っているということで…。 年甲斐もなく赤くなる顔を見られたくなくて、慌てながら帽子を深くかぶる私を見て夫が小さく笑っていた。 少し歯を出して口の片方だけを上げる笑い方は若い頃のままで、あの頃より皺は増えているけれど少年のような表情。 なんだか私までおかしくなってしまって笑みが溢れる。 辛いことや悲しいこと、負い目のような気持ち、そういうものをいつも一言で吹き飛ばしてくれる人。 改めて私は本当に良い人に貰われたんだなと、若い頃に感じた甘い気持ちが胸の奥に溢れてくる。 「…ふふっ、たまには若い気持ちで過ごすのも良いのかもしれませんね、あなた?」 雛子に子供が産まれるまでは遠慮もあったけれど、私ももう1人男の子を…という相談も今なら通用するかなとは思いつつ、これは後で夫が断れないタイミングで言ってやろうといたずらっぽい考えが浮かぶ。 「じゃあ、行きましょうか。」 そんな考えを誤魔化すようにサングラスを少しずらして、金色に光る目を見せてあえて幼くにっと笑ってみる…今ので逆に全部伝わってしまったような気もするけれど。 でもどちらでも構わない、この心地良い夫婦の瞬間を今は楽しみましょう。 気恥ずかしさを抑えて少しだけ大胆に、若かったあの頃のように軽く腕を組んで旅館へと歩みを進める。 腕から伝わる夫の温かさが下腹の疼きに流れ込んで、なんだか甘く痺れるようなものに変わる。 もしかすると生まれて初めてこの体質で迎える時間を楽しもうと思えているかもしれない。 …とん――。 旅館が近くなり迎えの人が見えてきた頃に私はほんの少しの間だけ頭を夫の肩に預けて、帽子越しに何度か狐の耳を撫でるように擦り付けてから腕を解く。 明確な意味はないし初めてしたことだけれど、夫はくすぐったそうにしながら耳を赤くしていた。 ――――…。








.gif)
.gif)

.gif)
.gif)
.gif)
_1064.gif)


.gif)
.gif)
.gif)
.gif)